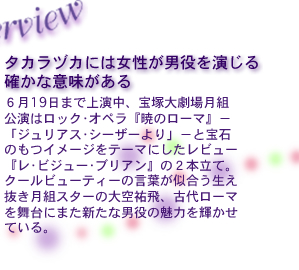6月19日まで上演中、宝塚大劇場月組公演はロック・オペラ『暁のローマ』−「ジュリアス・シーザーより」−と宝石のもつイメージをテーマにしたレビュー『レ・ビジュー・ブリアン』の2本立て。クールビューティーの言葉が似合う生え抜き月組スターの大空祐飛、古代ローマを舞台にまた新たな男役の魅力を輝かせている。
どんなに美しい男性でも、タカラヅカの男役の美しさ、魅力を表現することはできない。
「女性にしかわからないものが、理想の男性像です。私たちはそれを演じたいと思い、創り上げていく。その、創っている部分というのは、やっぱり夢の部分なんですよね。現実にはありえない、夢の世界だから美しい。もちろん、外見だけのことではありません。創る側にとっても男役は夢のある仕事だと思います」
男役の中でもクールビューティと言う言葉がピッタリする大空祐飛さん。素顔なのに、たった今、舞台から抜け出してきたように凛々しく、清清しいのは、さすが。一歩一歩着実に歩んできたスターだからこそ。
今年1月、大空祐飛さんは念願の『ベルサイユのばら』に男装の麗人オスカル役で特別出演した。男のように勇ましい女性の役と、男そのものを演じる男役が根本的に違うことを実感した大空さんは、男役とはどういうものかと改めて考えたという。
「オスカルを演じて思ったのは、とても女らしい人だということでした。私は14年間、男役をやってきて、男役の形が体に染み込んでいるんです。女らしい台詞を言っているのに脚が開いていたり、呼び止められて振り返る仕草が男性的だったり。女性で居続けることが1番難しかった。スカートをはいてしまえばなんでもないのに、オスカルの格好は男役と同じ。1秒ごとに女性であることを意識しなければなりませんでした。そのおかげで、宝塚の男役の魅力について新鮮な発見ができたのです」
つまり、タカラヅカでは女性が男性を演じる確かな意味が存在するのである。しかも世界中の人たちが認める男役の美しさは、男役の数だけある。
「黒燕尾服姿がきれいに見える体の角度は、先輩方が積み重ねてこられた伝統の上に、一人一人が自分らしさをプラスしたもの。私たちは常に新しい美しさに挑戦しているのです。当たり前のことですが、体形は人それぞれ。きれいに見える角度もちがうのですから」
1992年に初舞台を踏んだ翌年、月組に配属された大空祐飛さんの、新人公演時代を振り返ってみると、『ME AND MY GIRL』のジェラルド、『CAN−CAN』のエディエンヌ、『EL DORADO』のアロンソ、『WEST SIDE STORY』のトニー(第一部)、『黒い瞳』のプガチョフなどが、すぐ思い出される。マイペースで、ちょっとぶっきらぼうなところのある、魅力的な新人だった。
1999年に宝塚バウホール公演『十二夜』で見せたサー・トービーの軽妙さ。2001年にはバウホール公演『血と砂』にダブル主演し、02年、『長い春の果てに』では女役にも挑戦した。03年、『シニョール ドン・ファン』の、酸いも甘いも知った包容力ある大人の男のスティーブ・オースティン。04年、全国ツアー『ジャワの踊り子』のハジ・タムロン。『飛鳥夕映え』では蘇我石川麻呂と中臣鎌足を同期3人と役がわりで演じ分けた。
04年、『THE LAST PARTY』のフィッツジェラルド役でバウホール単独初主演。05年、『エリザベート』のルドルフ役では、運命にのみ込まれる薄幸の皇太子として舞台に登場した瞬間に目を奪われたのを思い出す。
「私は1段ずつしか階段を上ってきていませんが、だからこそ、1段1段を自分のものにしたいと思ってきました。そういうふうにやってきてよかったなと思います。どんな役もそのままの自分では演じられない。壁を乗り越え、自分の殻を破り、自分に足りないと思うものを積極的に取り入れてきた結果、今やっと、自分らしさってやっぱり大事だな、と思えるんですよ。自分が楽しいとか、自分が気持ちいいということが、結局、お客様に楽しんでいただけることにつながる。もちろん、お稽古場では苦しんだり、しんどい思いをたくさんしなければなりませんが、今自分の中がすごく充実しているんです。自分のペースをしっかりもって、自分らしい役づくりをしていこうと思っています」
 |