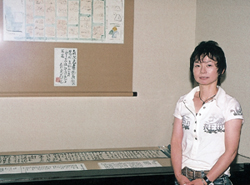| 私は漫画家を目指していたのですが、石森章太郎氏からデッサンを勧められ、花屋敷に住んでおられた洋画家の故平通武男氏に師事し、大学に入ってから水彩画を描き始めました。洋画は面、日本画は線で表現すると言われますが、私は線を意識して人物を描いています。
摸写は絵の勉強として重要ですが、洋画の場合は形の美しさを写し取るといった要素が強く、鉄斎のように人物の中身まで写し取る摸写とは違いますね。鉄斎は摸写といっても長谷川等伯の「千利休像」(前期展示)や谷文兆の「漁樵図」(前期展示)を写したもののように鉄斎流の力強い筆になっています。
私が特に興味を惹かれたのは摸写以外の旅日記のような「古宇津の山道図巻」(前期展示)や袈裟の模様を写したという「遠山衲衣略図」(写真塚本さんの左・前期展示)です。私も常に鉛筆とスケッチブックを持ち歩いていて喫茶店でお茶を飲んでいても、そのカップをスケッチしたりするんですが、鉄斎も矢立を携帯していてどこででも素描したんでしょうね。そして自分の引き出しに蓄積していった。
衲衣とは元々信者が奉納した裂きれをパッチワークのように縫い合わせて作られたそうですが、「遠山衲衣略図」は鉄斎が親しい僧侶から美しい如法の袈裟を借りて写したもので、それぞれの裂の色を覚書のように丁寧に書いていて、遠山衲衣への思い入れや色彩への関心が窺え、鉄斎の人柄までも身近に感じることができました。73歳にして好奇心、向学心旺盛だということにも驚きました。
この展覧会では、摸写以外の興味深い作品に触れることができましたし、原画のパネル展示もあり楽しむことが出来ました。
鉄斎美術館のある清荒神清澄寺の法主、坂本光謙師とは小学時代の同窓生でもあり、日本一の鉄斎コレクションを持つ美術館の存在を同級生として、宝塚市民としてもっとアピールしなければと思いました。 |